お金の問題ばかり頭に浮かんで、他のことに集中できない…。
こうした経験を持つ人は多いでしょう。
近年の研究により、貧困状態にいる人ほど思考力や集中力が落ちやすいことが示されています。
本記事では、アメリカでの実験やインドのサトウキビ農家の調査を通じてわかった「貧困と認知機能の関係」を解説します。
お金の悩みが脳を圧迫してしまう原因や、その対策のヒントまで一緒に見ていきましょう。
貧困による認知的負荷とは?お金の悩みがもたらす思考力低下
人間の脳には、一度に処理できる容量に限りがあります。
一度に複数の複雑なことを考えようとすると、頭が混乱してしまうのは誰でも同じです。
もし「お金が足りない」という問題が常に脳を占領していたらどうなるでしょうか。
これは単に気分的な落ち込みというだけでなく、脳の働き自体に大きな影響を与えることがわかってきました。
この点を端的に示すのが、アメリカのショッピングモールで行われた実験です。
研究者たちは買い物客に対して「車の修理代が高額になったとき、どうやって費用を工面するか?」を想像させ、その直後に図形推理や認知制御に関わるテストを実施しました。
その結果、経済的に余裕がある人は修理代が高くても認知テストのスコアがあまり変わらなかったのに対し、厳しい状況にある人はテストの正答率が大きく下がったのです。
この結果から、「貧しいから頭が悪い」というステレオタイプ的な考え方ではなく、お金の問題が頭を支配することで、他のことに使える認知資源が不足してしまうというメカニズムが見えてきます。
たとえるなら、スマホで重いアプリを常時起動している状態です。
バックグラウンドでずっと動いているアプリがバッテリーやメモリを消費していると、新しい作業に必要な処理能力が残らないわけですね。
貧困下の人ほど常にお金の悩みがバックグラウンドで動いているので、ちょっと複雑な思考や判断を要する場面でパフォーマンスを落としやすくなります。
また、この研究の興味深い点は、お金に余裕のある人に同じ金額の修理代を提示しても、脳を占領する度合いがさほど大きくならないということ。
高額な出費が想像しにくいほどの富裕層という可能性もありますが、それ以上に「そもそも余裕がある状態」は、ある程度の金銭的不安をうまく処理することができ、脳内のリソースが圧迫されにくいという解釈が成り立ちます。
サトウキビ農家から見る貧困と認知機能への影響
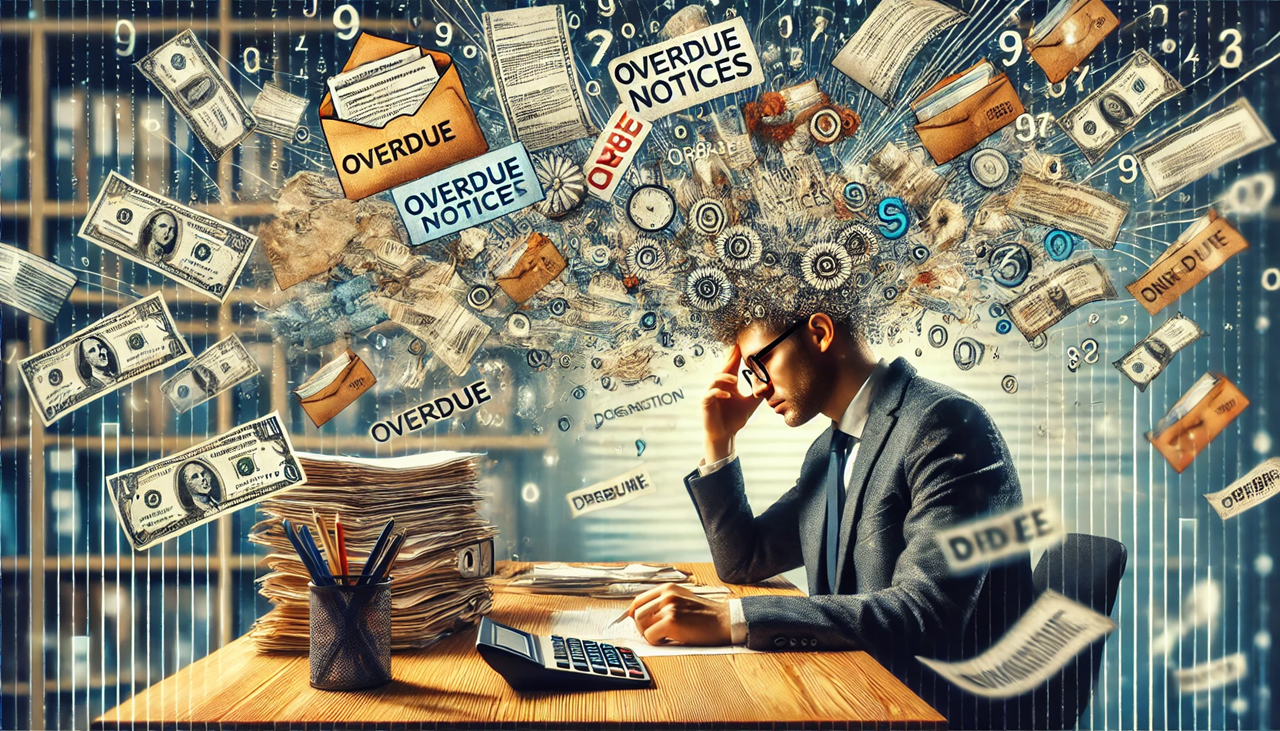
ここまでアメリカの事例を紹介しましたが、「貧困が人の認知機能に影響する」ことをさらに強く示すのが、インドのサトウキビ農家を対象にしたフィールド研究です。
サトウキビ農家は、年に一度の収穫時に大きな収入を得る一方、収穫前はどうしても金欠状態に陥りやすいという特徴があります。
この周期的な収入の増減を利用し、同じ農家を「収穫前」と「収穫後」のタイミングで比較したのです。
結果は非常にわかりやすく、収穫前の農家は認知テストの正答率が低く、反応速度も遅いのに対し、収穫後は大きく改善することがわかりました。
研究者がさらに詳しく調べたところ、栄養状態や身体的疲れといった要因だけでは説明できないほど、テスト成績にはっきりとした差があったのです。
収穫前は借金が増え、日々の支払いに追われるため、お金の心配がつきまといます。
一方、収穫後には借金を返済し、ある程度手元のお金に余裕ができるので、頭から「お金が足りない」という不安が消えやすい。
すると、脳のキャパシティが回復し、結果的に思考力や集中力が上向くのです。
ここで重要なのは、同じ人でも「貧しい状態」と「比較的余裕のある状態」に置かれると、認知機能のパフォーマンスが大きく変わってしまうという点です。
この変化が生まれる要因を分析すると、お金に関わるタスクが脳内の優先度を最上位に押し上げてしまうという仕組みが見えてきます。
要するに、貧困そのものが認知リソースを奪う大きなトリガーになるということです。
まとめ
こうした研究が教えてくれるのは、貧困状態は単なる金銭不足にとどまらず、人の思考や行動にまで強い影響を及ぼすという事実です。
金欠になると健康的な選択を先送りにしがちだったり、仕事のパフォーマンスを下げてしまったりすることもあるかもしれません。
それがまたさらなる経済的不安を招き、悪循環にはまり込むリスクが高まります。
一方で、政策や支援策の観点からは、「複雑な申請手続きや長時間の面談を貧困層に強いると、かえって逆効果になる可能性がある」という示唆も得られます。
経済的に苦しい人々は認知リソースが少ない状態にあるため、難しい書類を何枚も書かせたり、複雑な条件をいくつも示されたりすると、それだけで混乱してしまうことが考えられます。
結果として本来受けられるサポートが届かないという事態を招かないよう、手続き自体を簡素化したり、わかりやすいサポート体制を作ったりするのは非常に重要です。
個人レベルでの対策としては、タイミングや環境を工夫してお金の悩みを少しでも和らげるアクションをとることが挙げられます。
大事な決断や集中力を要するタスクは、できるだけ金銭的不安が小さいタイミングで行うようにするとか、日常の支払いをオートメーション化して頭の負担を減らすなどの方法です。
また、もし急に大きな出費が重なってしまったら、まずは不安を紙に書き出して優先順位を明確にするだけでも認知的負荷を軽減できる場合があります。
「貧困」と「認知機能」の関係を理解すると、お金に関する悩みが思いのほか大きいことに気づきます。
お金の話というと、倫理的な側面や自己責任論に陥りがちですが、実際には脳内リソースの使い方という視点が深く関わっているのです。
ここまでご紹介した研究結果を参考にして、自分自身や周囲の人が思考力を奪われる状態に置かれないよう、意識的に対策をしてみるのもいいかもしれません。
お金の悩みが常につきまとう状態は、確かに苦しいものです。
しかし、その状況が自分の思考まで縛っていると気づければ、少なくとも対策の必要性や有用性を強く感じられるのではないでしょうか。
まずは「今、頭の中がお金の問題でどのくらい占められているか?」を客観的に振り返ってみることから始めてみましょう。
参考文献
Poverty impedes cognitive function.
https://www.science.org/doi/10.1126/science.1238041



